【vol.33】インターバルの位置関係を、目でも覚える
(※この記事の講座を含む、現在プレゼント中の教材(総数10講座~、合計1000p~)は、こちらのページから完全無料でダウンロードが可能です)
こんにちは、大沼です。
さてさて、ここ最近続いていたインターバルの基本も、今回と次回でひとまず終わります。
慣れないうちは、考えるのに時間がかかったり、ローマ数字が読みづらかったりで、結構大変でしょう。
僕もこの辺りを勉強し始めた頃は、何をするにも時間がかかっていた記憶があります。
楽曲の分析をする時は、その曲のキーのダイアトニックコードを全部紙に書き出して、一つ一つ確認しながら練習してましたからね。
やはり不慣れなものを扱う時は、それなりの労力が必要になってきます。
ただ、キーとコード、インターバルのそれぞれの関係性がわかっていないと、これまで覚えてきたスケールやらなんやらをちゃんと活用することが出来ません。
ギター上達に対する向上心が高く、勉強熱心な人の中には、実は
『スケールやコードはそれなりに覚えているけど、使い方がわからない』
みたいな人が結構いたりします。
(※特に独学でやっている人に多い気がしますね)
その使い方がわからない原因は、今、この講座で学んでいるような知識と覚えているスケールやコードが結びついていないからです。
大きく捉えるならば、
『楽曲を構成している要素との関係性がわからないから』
とも言えますね。
そのせいで、せっかく覚えたものも生かせない、と。
この辺りの「使い方」の部分は、今までの知識を総括した実戦的な内容になります。
なので基本的な理論の部分をある程度やってしまわないと、話を進められないんですね。
ここがもう少しでひと段落するので、その後、実戦に入っていきましょう。
と、言う事で、今回やることは、
『これまで勉強していたインターバルを、指板上でどの様に見たらよいのか?』
についてです。
前回までの内容とはちょっと違い、考える、と言うよりは単純に覚える作業ですね。
『トニック(やルート)を設定したら、その音から見て、指板上のどこにどのインターバルがあるのか?』
これをさらっと覚えてしまいましょう。
と、言う事で、まずは、トニックやルート音として、スケール、コードの両プレイ時に基点とする、5、6弦上のインターバルから見ていきます。
この位置感覚を身につける事により、key、ダイアトニックコード、ダイアトニックスケールをスムーズに把握できるようになりますので。
いつものように、基準音をC音に設定して、key=Cで考えていきましょう。
把握するインターバルは、メジャーキーならばメジャースケールのインターバルになるので、tonic(1st)、M2nd、M3rd、P4th、P5th、M6th、M7thの位置になりますね。
まず、基準となるC音(今回のtonic)の位置として、一番最初に思いつくであろう場所は、5弦3フレットと6弦8フレットの位置ですね。
この2箇所のどちらからみても、メジャースケールのインターバルのそれぞれの位置をパッと判別できるようになりましょう。
と、言う事で指板図はこちらです。
図、5、6弦上のCメジャースケールのインターバル
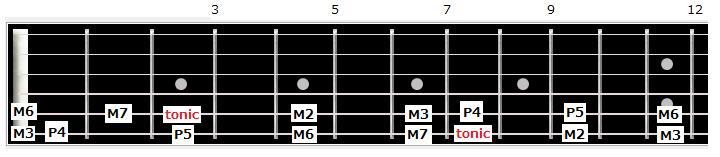
ある音をトニック(ルート)とした時、全体の基本的な位置関係はこのようになりますね。
これを覚えて、弾きたい音をパッと弾けるようにする、と言うことです。
現時点でも、ギターを弾き始めて一番最初の、基本的なコードを覚えていく時の名残で、ある程度はすぐにわかるのではないかと思います。
とは言え、いきなり図を出されて「さあ覚えましょう」と言われても、中々大変なところもあると思うので、いくつか覚え方のポイントを挙げていきますね。
まずは単純に、一番わかりやすいのはM2ndの位置でしょう。
これはトニックの2フレット先なので簡単です。

次にトライアドのトレーニングで覚えた、M3rdとP5thの位置。
この位置関係は超重要なので、早めにマスターしておきましょう。実際の演奏でもよく使います。
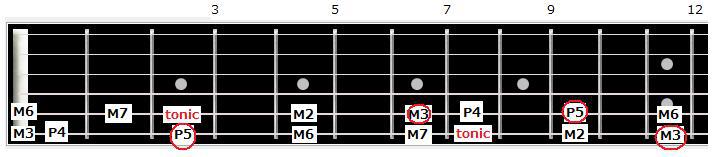
これらを踏まえた上で、残りのインターバルは、M7thはトニックの1フレット左(半音下)ですし、P4thはM3rdの隣(音上)もしくはトニックの真下、M6thはP5thとM7thのちょうど中間にあります。
後、P5thはトニックの真上(低音弦側)とも見る事が出来ますね。
こんな感じで、ハッキリ言ってしまえば覚え方は自由です。
これらの位置を基準に見て、
覚えたインターバルのそれぞれの音をルートにした場合、メジャーキーのダイアトニックコードとしては、どんなコードが構成されるのか?
これと結びつけばOKです。
(※例えばCキーで、M2ndのD音をルートにした場合のダイアトニックコードはDm7(Ⅱm7)というように、位置とコードの種類がわかること)
先ほども書きましたが、このインターバルの位置の覚え方は自由です。
普段のスケールトレーニングの最中でも1音ずつ確認しながら練習していけば段々とわかってきますし、実際の曲を弾きながら覚えてもいいですね。
以前やった、Let it beなどはちょうど良いサンプルでしょう。
この様なインターバルの位置関係は、最終的には全弦で覚えるのですが、まずは基準として見やすい5、6弦から覚えていきましょう。
全弦で覚えるのは大変そうに感じるかも知れませんが、ギターの構造上、1オクターブ上のポジションが視覚的にわかりやすいので、そこまで苦労はしません。
その理屈でいくと、今の段階でも、5、6弦を覚えれば、オクターブ上の3、4弦のインターバルの位置がある程度わかるはずです。
こんな感じで、ギターの構造を理解して複合的に考えていくと、効率よくマスターできますね。
後はやはり継続です。
1日1回でも良いので、インターバル把握のトレーニングを行っていれば、単に音の並びに1~7までの番号(とアルファベット)が振ってあるだけなので、意外とすぐに覚えられたりしますから。
それでは、今回は以上になります。
ありがとうございました。
大沼
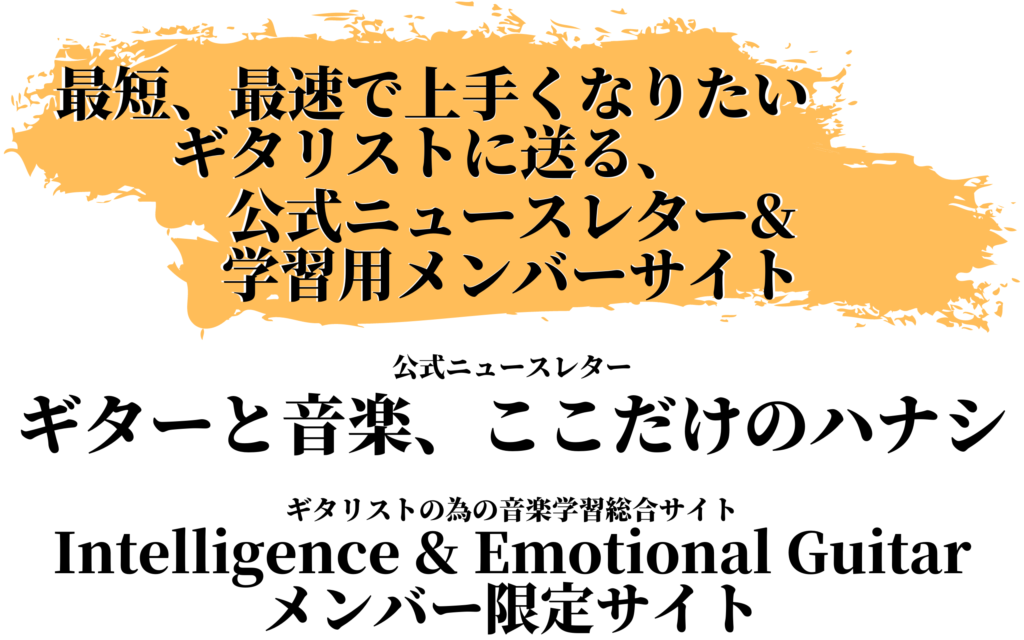
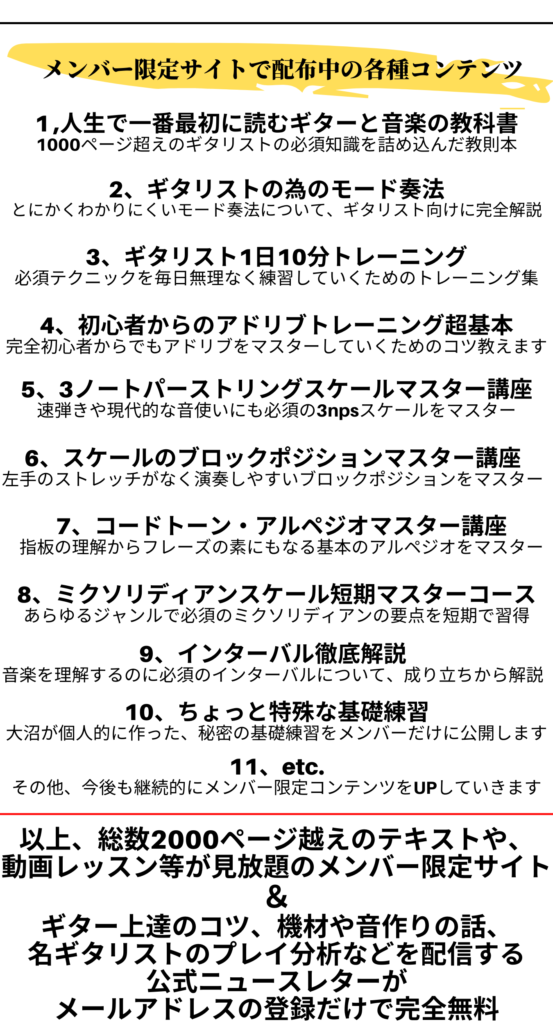
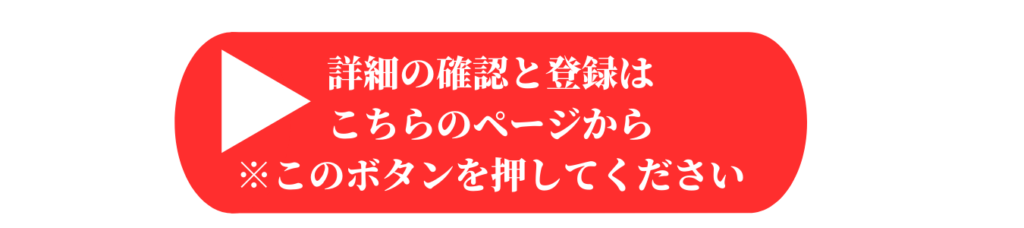

この記事へのコメントはありません。